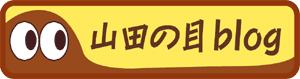山田工業社員の目から見た日常をお伝えします。
| ← | 2026年2月 | → | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
28 | |
| 最近の記事 |
| 慈恩寺1200周年
|
| 古式・棚地形復刻 |
19:55, Monday, Nov 16, 2009 ¦ 固定リンク
■コメント
| 当日は失礼いたしました。 古式な雰囲気のある棚地形でした。 木遣りの歌が作業のタイミングになっているのがよくわかりました。 また、ほんとにタイミングがあわないと危険な作業だと思いました。 ありがとうございました。 |
| 明治の初期、東京大学のお雇い教授として来日し、大森貝塚の発見者として有名なアメリカ人生物学者のエドワード・S・モース博士が、著書のなかで次のように書き残しています。 「運河の入り口に新しい治水が築かれていた。 不思議な杭打ち機械があり興味が尽きない。 縄を引く人は八人で円陣を成し単調な歌が唄われ 一節の終わりに揃って縄を引き、おもりはドサンと落ちる。 少しもおもりを揚げる努力をしないで歌を唄うのは 誠に馬鹿らしい時間の浪費であるように思われた。 時間の十分の九はただ歌うを唄うのに費やされるのだ」 これが、アメリカ人の見た「木遣」のイメージです。 |
| 最近のコメント |
| 最近のトラックバック |
| 携帯で読む |