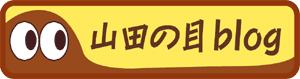山田工業社員の目から見た日常をお伝えします。
| ← | 2026年1月 | → | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 |
|
29 | 30 | 31 | |
| 最近の記事 |
| 慈恩寺1200周年
|
| 取材 |
| 本日、取材を受けました。 ・・・・事情聴取じゃありませんヨ。 なんでも、市内の高校の図書館や職業安定所、市営図書館、公民館などに顔写真入りで配布されるそうです。 さいたま市経済局経済部労働政策課労政係というところから依頼され、特に若い人向けにいろいろな職種の人にインタビューして、『技能職ガイドブック』という冊子を作るのだそうです。 私自身も『鳶職』って、どんな職業なのかって小中学校のころ担任の先生やクラスメートから尋ねられても、ハッキリ答えられた記憶がありません。 何しろ『鳶職』は職域が広くて、いわば建築界の何でも屋的な色が濃いです。 土木工事、基礎工事、杭工事、コンクリート工事、鉄筋工事、解体工事、木造・鉄骨組み立て(建方)工事、足場工事、ブロック工事、石工事、外構工事、造園土木工事、曳き家工事、重量物運搬・据え付け工事、橋梁工事・・・数え上げればキリがありません。 しかしながら、これら全てをこなせる職人はいません。 今はそのほとんどが分業化してしまい、鳶頭であっても基礎屋さん、足場屋さん、外構屋さんなんて呼ばれる始末ですが、仕事だけしか出来ないのであれば仕方の無いことかもしれません。 少なくとも、『鳶職』、『頭(かしら)』と呼ばれるには、仕事の外に半纏(はんてん)正装で『木遣(きやり)』ができて『梯子乗り』、『纏(まとい)振り』といった伝統技芸を習って初めてだと考えます。 江戸時代の鳶職は、町お抱えの用務員さんのような役割でした。 火事が起きれば、現在のように火に放水して消火するのではなく、延焼の恐れのある火事になっていない建物を壊して空き地を作り、そこで火事を止めたのです。これを『破壊消防』と言います。 つまり火事=解体工事だった訳です。 もちろん、火事場の片付けの後は新築です。 鳶職は頭(かしら)とも呼ばれ、材木屋、大工、左官、建具屋、畳屋などいろいろな職人を呼んできて建物を作る、今で言う総合建設業の役割をしていました。 また、町で冠婚葬祭があれば、その面倒を見る、土葬の墓穴を掘る、祭りがあれば神輿や山車の面倒を見る・・・ 『義理と人情とやせ我慢』の心意気が現在の日本の若者にメッセージとして届くでしょうか? 冊子の出来上がりが楽しみでもあり、不安でもあります。 |
22:16, Wednesday, Feb 24, 2010 ¦ 固定リンク
■コメント
| 最近のコメント |
| 最近のトラックバック |
| 携帯で読む |